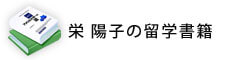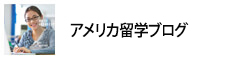留学生と留学志望者が心得ておくべき就職事情

一時帰国した留学生に真っ先に聞くこと
冬休みになると、当研究所からアメリカの大学に留学している学生が一時帰国して、よくオフィスに訪ねてきてくれます。
そんな時、私は開口一番成績のことを聞きます。
そしてGPAが3.9なんて聞くと、自分のことのようにとても嬉しく感じます。
日本の大学生は、他人に成績を聞かれることもまずありませんし、そもそも気にすることもないと思いますが、アメリカでは成績がとても重要です。
就職する際にも、大学院に進学する際にも、奨学金支給の有無もすべて大学の成績が問われるからです。
たとえばハーバード大学やUCLAなんかも合格者のGPAは3.75以上が当たり前です。
また、大学での成績優秀者は卒業式で表彰され、ラテン語で書かれた表彰状をもらいます。
GPAが3.5以上の学生、3.75以上の学生、というように、表彰のレベルも細かく分かれています。
それくらいアメリカ社会では成績が重視されているのです。
就職のことを考えていない留学生はのん気?
さて、アメリカの大学に入ってまだそれほど年月が経っていない留学生が、家族そろってオフィスに訪ねてくれました。
そのとき一緒に来たお兄さんがこんなことを聞いてきたのです。
「弟はのん気にアメリカの大学に行っているが、そんなことで就職は大丈夫なのか?」
このお兄さんは、日本の大学4年生で、就職活動にたいへん苦労し(外国でインターンシップもしたそうです)、その苦労が実って、良いところに就職できたそうです。
それに比べて、留学中の弟は何も考えていないことが我慢ならない。
当研究所ではいったい就職についてどういうアドバイスをしているのか、ということを言いたかったようです。
留学の動機は道を探すための「時間かせぎ」でもいい
日本では、受験にしても就活にしても、「右へならえ」という傾向が、ますますヒドくなっています。
これだけインターネットが発達して、世界中の多様な意見が飛び交っているのに、どうして受験と就活は「一つの道」しかないんでしょうか。
いま働きざかりの40代・50代の人に、「あなたどうしてその仕事してるの?」と聞いても、ほとんどの人は「たまたま」と返事します。
留学カウンセラーが天職だと言われる私でも、この仕事は「たまたま」なんです。
学生さんは、就職の際にもっともらしい自己PRや志望動機を作ってきますが、そういうのもただ本人が思い込んでいるだけ。
18歳~22歳で自分の将来をはっきり決められるものですか。
まだ社会の仕組みや働く意味、これから社会で自分が何をしてどう生きていくのがなどわかるはずもありません。
私だって大学を終える頃に、社会に出るのが怖くて、何をしたいのかわからず、ある意味時間かせぎでアメリカの大学院に行ったようなものです。
そのお兄さんに「それであなたどこの会社に決まったわけ?」と聞いたら「○○」という返事。
「エッ、それってAI(※人工知能)に一番初めに取って代わられそうな仕事じゃないの!」と、年甲斐もなく意地悪を言ってしまいました 笑
就職先が問われる時代はもう終わる
就職先でどんなに本人が努力しても、倒産、リストラ、買収、そのうえ天災、事故など、さまざまなことが起こり得ます。
大企業に入社できたから一生安泰なんて、それほど人生は単純じゃないんですよ。
例えば出世に関したって、社長をはじめ役員など会社で最後に勝ち残れる人は10人程度。
自分の同期をはじめ、5年前後に入社した同年代の社員全てがライバルなのですから、単純に確率は1,000分の10くらいでしょうか。
そんな数%もないようなレースに自分の半生かけるのは、そもそも健全な生き方なのでしょうか。
また、技術の発展が著しいこの時代で、企業が何十年も安泰ということ自体が怪しいもの。
インターネットやスマホの登場で、テレビや出版、音楽、映画、物流、メーカー、販売店など、多くの大企業が業績をさげ、そのいくつかは存続すら危ぶまれています。
昭和の時代のように、毎日会社にまじめに通勤してれば、年次と共に自然に出世してお給料も上がっていくなんていった制度や概念自体がそもそも危ういのです。
アメリカで、こういったテクノロジーの開発にかかわる企業の人たちは、「あと20年くらいで、失業率は30%くらいになる。そもそも一人の人間がずっと同じ一つの仕事をするなんてことはあり得ない。一人が二つも三つもの仕事をしたり、数年ごとに仕事が変わったりする時代になる」と言っています。
というのもAI(※人工知能)がおそろしいスピードが発達しているからです。
いまに人間の仕事のありかたや生きかたを変えてしまうことでしょう。
これからは、「自分とは何か」「自分の生きる道は何なのか」ということをもっともっと深く考えて生きなければならない時代になっていきます。
とてもよい条件だと思っていた仕事が、突如としてそうでなくなったりもします。
ですから、つねに「自分は何が好きなのか」「どんなことをしているときが自分は生き生きしているのか」を考えて、仕事や生きかたを探していかなければならないのです。
留学の「出口」は就職だけじゃない
ある企業の人が、アメリカのリベラルアーツ・カレッジ(※)に在学している留学生に会って、その企業がこれから求める人材かどうかを見てみたいということで、いくつかの大学を紹介したことがあります。
そんな彼は何人かの留学生に会った後、こう言ってきました。
「いやー驚きました。わが社に是非入ってもらいたい人たちが見つかったのですが、どの人も『大学院に行くかも』とか『ちょっとアフリカに2年くらい行こうと思っている』とか、いろいろ計画があって、就職はお呼びじゃないということでした。残念です。なかなか合わないものです。。。」
このように、就職は本人の努力や希望だけではなくて、運や縁などさまざまな条件がからまり合って成り立つのです。
※リベラルアーツ・カレッジ:小規模(学生数が1,000〜3,000人くらい)の私立四年制大学。研究よりも「教育」に力を入れていて、幅広い教養を身につけたリーダーを育成する。学生たちは自然に抱かれたキャンパスで寮生活を送る。
留学とは、就活にとらわれない生きかたを選ぶこと
世界中の学生を見渡すと、大学の勉強そっちのけで就活活動にいそしむのは日本だけです。
(アメリカの大学では、大量のレポートや課題など求められることが多く、卒業の条件が非常に厳しいため在学中は勉強に全力で集中しないといけません。ですから就職活動は、大学を卒業して、時には1年ぐらい休んでからというのが一般的ですし、一つの季節にみんなが一斉入社という習慣もありません。その分、学ぶことに真剣になれます。)
しかも入社3年で3分の1の人が辞めるというではないですか。
いまどき企業側も新卒だけでなく、留学経験がある日本人や、在日中の外国人など、さまざまなチャンネルを設けて、年中、人材を探しています。
当研究所から留学した人の中には、この間までシンガポールで働いていたのに、いまは香港で働いているといった人もたくさんいます。
ちょっと経歴のおもしろい人なんかは、世界中のヘッドハンターがつねに追いかけてきます。
そういう人は、自分で起業するにしたって、就職するにしたってさまざまな可能性や選択肢に溢れてんです。
逆にいえば、大企業などは、日本の一般的な大学生のように「ただ3年生になったから髪の毛を黒く染めて、慣れないスーツをきて、それらしい自己PRや志望動機を述べる人」では物足りないんですよね。
もちろん大企業などは規模の大きさもあってそういう学生を一定数必要とする面もありますが、そうでない個性的な人、つまり「違う考え方や価値観、スキルをもつ人」を強く求めているからこそ前述のようなことが起きるのです。
こういった複雑な社会において、たくさん勉強をして、色々な仕事や会社をみて、多くの人と出会い、自分自身が様々な仕事を経験して、何年もかけてやっと見つかるかどうかというのが自分の「天職。」
だから、大人は学生に「なんでこういう仕事を?」と聞かれると、説明できる時間も足ないし、「まぁ全部言ったって若いしわからんだろうなぁ・・・」と思って、とりあえず「たまたま」となってしまうのでしょう。
まぁ人生、一言二言で片づけられるものなわけがありません。
ましてや何の実績もない22歳あたりの就活の出来で人生全て決まるわけないでしょう。
『大学在学中の就活が人生を決める』と若者に洗脳する日本の教育って何なんでしょうね。
人気記事
- 留学がすべてのはじまり-私の留学- 第1回
- 留学するのに“目的”を求めること自体がくだらないワケ
- 日本人留学生だけが知らない?!アートを学んで得られる本当のメリット
- 奨学金だけじゃない!知られざる留学費用の節約方法
- 学生が陥りがちな交換留学と認定留学の罠
- "返済不要!留学生が知っておくべき奨学金あれこれ
- "今でしょ!"林修先生とTV番組で共演しました!
- 16~17歳でアメリカの大学に「飛び級」で留学する方法&するべき学生
- スポーツ留学を本気で目指す学生に必要な覚悟と現実
- ホームステイからはじまる残念な留学
- 留学の幻想を振り払う 前編
- 留学の幻想を振り払う 後編
- 日本地図からの脱出 前編
- 日本地図からの脱出 中編
- 日本地図からの脱出 後編
▼ 読むだけでアメリカ留学に役立つ資料をお送りします。▼
著者情報:栄 陽子プロフィール

栄 陽子留学研究所所長
留学カウンセラー、国際教育評論家
1971年セントラルミシガン大学大学院の教育学修士課程を修了。帰国後、1972年に日本でアメリカ正規留学専門の留学カウンセリングを立ち上げ、東京、大阪、ボストンにオフィスを開設。これまでに4万人に留学カウンセリングを行い、留学指導では1万人以上の留学を成功させてきた。
近年は、「林先生が驚いた!世界の天才教育 林修のワールドエデュケーション」や「ABEMA 変わる報道番組#アベプラ」などにも出演。
『留学・アメリカ名門大学への道 』『留学・アメリカ大学への道』『留学・アメリカ高校への道』『留学・アメリカ大学院への道』(三修社)、『ハーバード大学はどんな学生を望んでいるのか?(ワニブックスPLUS新書)』、ベストセラー『留学で人生を棒に振る日本人』『子供を“バイリンガル”にしたければ、こう育てなさい!』 (扶桑社)など、網羅的なものから独自の切り口のものまで、留学・国際教育関係の著作は30冊以上。 » 栄陽子の著作物一覧(amazon)
平成5年には、米メリー・ボルドウィン大学理事就任。ティール大学より名誉博士号を授与される。教育分野での功績を称えられ、エンディコット大学栄誉賞、サリバン賞、メダル・オブ・メリット(米工ルマイラ大学)などを受賞。

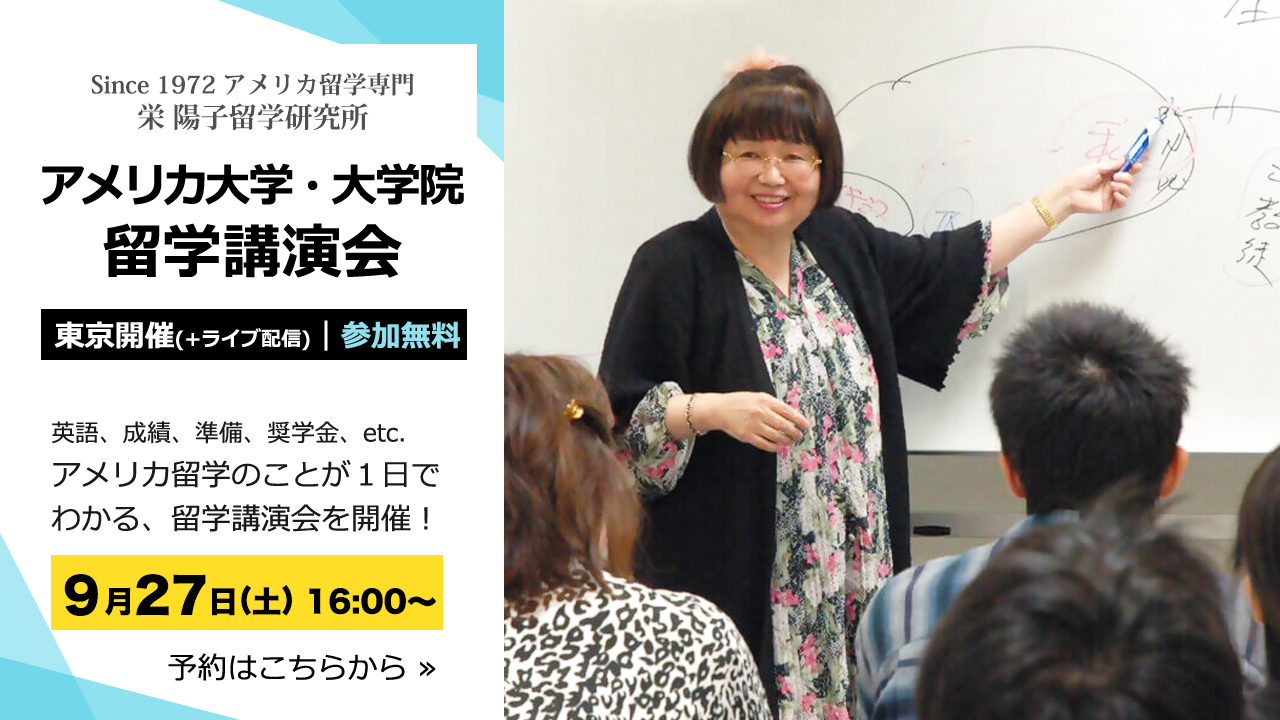
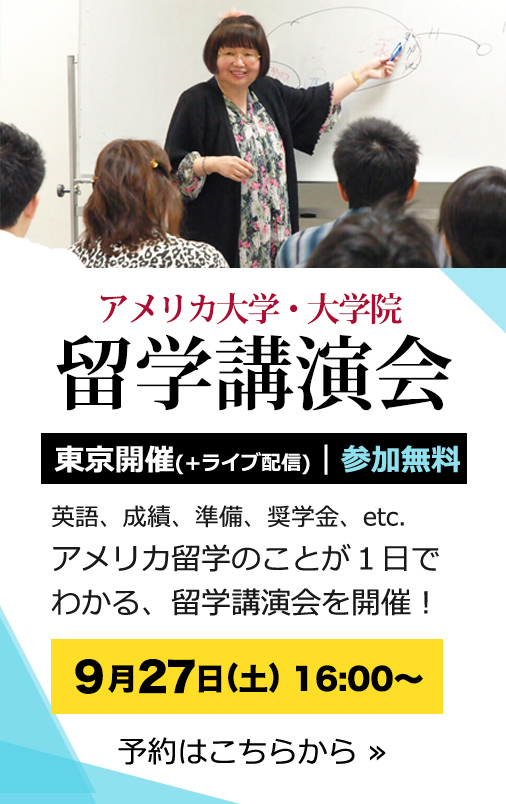
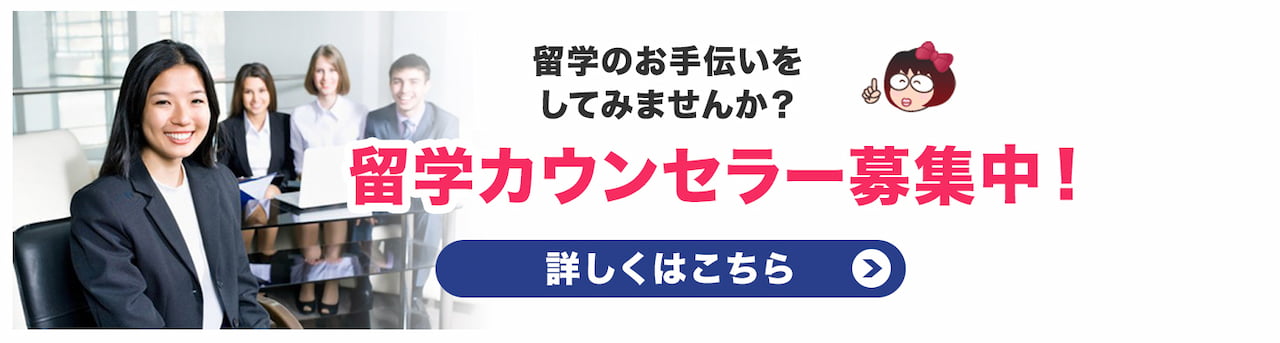



.jpg&w=525&h=390)
.jpg&w=525&h=390)